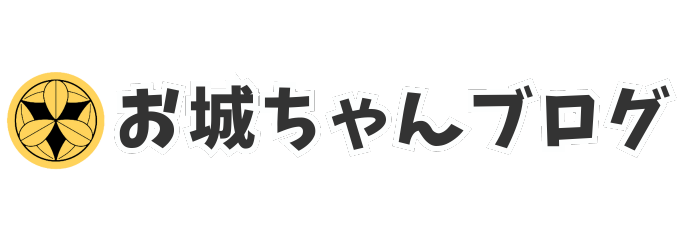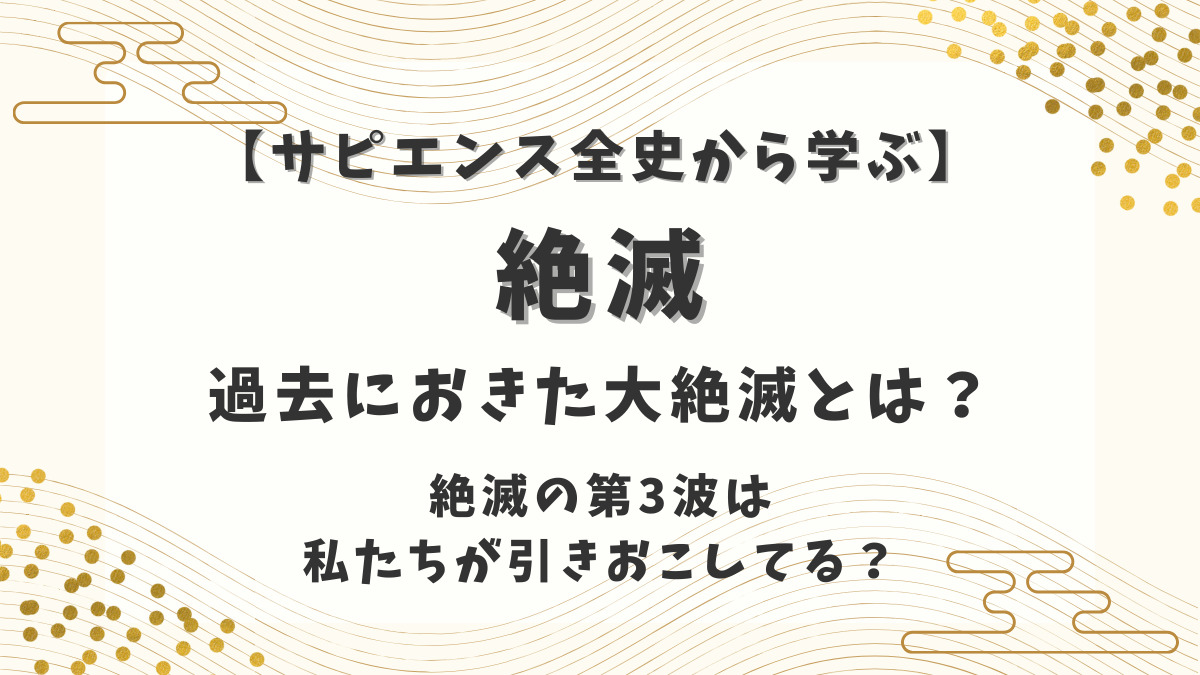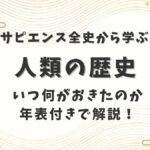【AD】広告を含みます。
地球上で起きた「絶滅の第1波、2波、3波」ってご存知ですか?
一般的に「絶滅」と聞くと「恐竜」を思い浮かべる方も多いのではないのでしょうか?
しかしここでいう「絶滅」は恐竜の絶滅のことではありません。
また「絶滅の第3波」は私たちが現在引き起こしているともいわれています。
少しでも気になった方はこの記事を最後まで読んで一緒に学んでいきましょう。

この記事は「絶滅の第1波、2波、3波」についてわかりやすく解説しています。
「サピエンス全史/ユヴァル・ノア・ハラリ」を参考に作成しています。
-

-
【サピエンス全史】から学ぶ人類の歴史!何年に何があったのか年表付きで簡単に解説【前編】
【AD】広告を含みます。 私は歴史を調べていく過程で人類史に興味を持ちました。 そこで名著として世界的に大ヒットしている「サピエンス全史 / 著 ユヴァル・ノア・ハラリ」を読んで学びましたのでぜひ皆さ ...
続きを見る
動植物の大規模な絶滅が3回おきた
地球上の長い歴史の中で大規模な動植物の絶滅が大きく3度起こりました。
その1回目のことを「絶滅の第1波」
2回目のことを「絶滅の第2波」
3回目のことを「絶滅の第3波」とよんでいます。
要約すると
絶滅の第1波 → 約4万5000年前にホモサピエンスがオーストラリア大陸に上陸したことによって引き起こされた
絶滅の第2波 → 約1万6000年前にホモサピエンスがアメリカ大陸に上陸したことによって引き起こされた
絶滅の第3波 → 約200年前に産業革命が起きたことによって引き起こされ、現在も継続中
となります。
次からひとつひとつ詳しく解説していきます。
絶滅の第1波について
絶滅の第1波は約4万5000年前にホモサピエンスがオーストラリア大陸に上陸したことによって引き起こされます。
人類のオーストラリア大陸への到達は、歴史上屈指の重要な出来事です。
これは「コロンブスによるアメリカへの航海」や「アポロ11号による月面着陸」に匹敵します。
さらに大事なことは、開拓者であるホモサピエンスがオーストラリア大陸で「したこと」です。
人類はそれまでに革新的な適応や行動をしてきましたが、それが環境に与えた影響はほとんどありませんでした。
つまりさまざまな生息環境に移動し、順応するという成功をおさめてきましたが、生息環境を大きく変えるということはありませんでした。
オーストラリア大陸を開拓したホモサピエンスはただ順応しただけでなく、この大陸の生態系を元の面影がないほどに変えました。
オーストラリア大陸には、それまで人類が目にしたことのない未知の生き物が暮らしていました。
オーストラリア大陸にいた巨大生物
- 体重200kg、体長2mのカンガルー
- 現生のトラほど大きい有袋類のフクロライオン
- あまりに大きすぎて抱っこしたいとも思えないようなコアラ
- ダチョウの2倍の大きさの飛べない鳥たち
- ドラゴンのようなトカゲ
- 長さ5mもあるヘビ
- 巨大なディプロトドン(2.5トンもあるウォンバット) など
鳥と爬虫類を除けばこれらはみな「有袋類」です。
有袋類は自分ではなにもできない極小の胎児を産み、その胎児をお腹の袋の中で母乳育児します。
有袋類の哺乳動物はアフリカやアジアでは非常に珍しかったのですが、オーストラリア大陸の生き物はほとんどが有袋類でした。
その後数千年のうちに、これらの巨大生物は事実上全て姿を消しました。
体重が50kg以上あるオーストラリア大陸の動物種24種のうち、23種が絶滅しました。
これより小さい種も多数が絶滅しました。
これは何百万年もの間で、オーストラリア大陸の生態系における最も重大な変化でした。
大規模な絶滅は気候変動のせいではない
大規模な絶滅が起きるとそれは気候変動が起因してのことだと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかしこの大規模な絶滅にホモサピエンスが関与していたことを示す根拠が3つあります。
根拠1:あまり著しい気候変動ではなかった
およそ4万5000年前におきたオーストラリア大陸の気候変動はあまり著しい変動ではありませんでした。
今日、なにかと気候変動のせいにする風潮がありますが、実際には地球の気候が現状にとどまり続けることはありません。
歴史上のどの出来事も何らかの気候変動を背景に起こっています。
特に地球は寒冷化と温暖化のサイクルを数えきれないほど経験しています。
過去100万年間には平均すると10万年ごとに氷河時代がありました。
最後の氷河時代は7万5000年から1万5000年までですが、氷河時代としては特別厳しいものではありませんでした。
ディプロトドンは150万年以上前からオーストラリア大陸に生息し、氷河期を10回以上経験しましたがうまく切り抜けています。
しかし4万5000年前にホモサピエンスがオーストラリア大陸に上陸してから、ディプロトドンだけでなく他の大型動物の9割が姿を消しました。
根拠2:海洋生物は無被害
気候変動が大規模な絶滅を引き起こすときには、たいてい「陸上生物」とともに「海洋生物」にも大きな被害が出るものです。
しかし、4万5000年前に海洋動物が著しく消失したという事実がありません。
根拠3:同じことが何度も繰り返されている
このオーストラリアでの大規模な絶滅と同じようなことがその後何度か繰り返されています。
ホモサピエンスが新たな地域に住み着くたびに大型動物相の絶滅が起こっています。
大型動物相絶滅の事例
- 4万5000年前の気候変動を無傷で切り抜けたニュージーランドの大型動物相は、人類が最初に上陸した直後に壊滅的な被害を被っています。最初の開拓者であるマオリ人は、800年ほど前にニュージーランドに上陸しました。その後200年のうちに、大型動物相の大半と、全鳥類種の6割が絶滅しました。
- 北極海にあるウランゲリ島(シベリアの海岸から200m北にある島)のマンモスにも同じことが起こりました。北半球のほとんどでマンモスは何百万年にわたって栄えてきましたが、ユーラシア大陸→北アメリカ大陸とホモサピエンスが拡大するのと並行して数が減少していきます。1万年前には大陸のどこを探してもマンモスが見られなくなりました。唯一の例外がウランゲリ島で、大陸でマンモスが見られなくなったあともこの島ではマンモスが6000年程栄え続けていました。しかし、約4000年前にホモサピエンスが初めてこの島に辿り着いてから、マンモスはこの島でも見られなくなり絶滅してしまいました。
これらの根拠を踏まえると、大規模な絶滅にホモサピエンスが関与していたと考えるのが妥当です。
どのようにして絶滅に追い込んだの?
実際にホモサピエンスがどのようにして大型動物を絶滅に追いやったのか、それには3つの方法があったと考えられています。
狩るペースが動物の繁殖期間を上回る
大型動物は繁殖に時間がかかります。
妊娠期間が長く、1回の妊娠で生まれる子どもが少なく、次の妊娠までの期間が長いです。
その結果、人類が数ヶ月に一度、1頭でもディプロトドンを狩ればそれだけでディプロトドンの死亡率が誕生数を上回ってしまいます。
さらにホモサピエンスは狩猟の腕が高かったため、大型動物を狩るのは容易なことでした。
大型動物はホモサピエンスが危険な種であることを知らなかったので、人類に対する恐れを進化させる前に絶滅してしまいました。
焼き畑農業を行う
ホモサピエンスはオーストラリア大陸に到達する頃にはすでに焼き畑農業を習得していたと考えられています。
通り抜けられない藪や密林は意図的に焼き払い、草地を生み出しました。
そうすることで狩りがしやすくなったり、生活を営みやすくなりはしたものの生態系を大きく変えてしまいました。
ユーカリが繁殖した理由
ユーカリの木は4万5000年前はオーストラリア大陸では珍しい植物でした。
しかしホモサピエンスが上陸し焼き畑農業を行うと、他の高木や低木は姿を消しましたが火に非常に強いユーカリの木は広く分布することとなりました。
植生が変わるとそれを食べる動物や、それらの草食動物を食べる肉食動物に影響を与えます。
ユーカリの葉を食べるコアラはオーストラリア大陸全土に広がっていきましたが、ほとんどの動物は絶滅に追い込まれることになりました。
気候変動の影響も無視することはできない
先ほど大規模な絶滅は気候変動のせいではないといいましたが、やはり気候変動の影響は完全に無視することはできません。
気候変動がおきると生態系が安定を失い、脆弱になります。
通常の状態であれば多少の被害があっても生態系はまた回復することができます。
しかし、気候変動がおき生態系が脆弱な状況の下でホモサピエンスが上陸しました。
そのことがもろくなっていた生態系を奈落の底に突き落としたと考えます。
気候変動と人間による狩猟の組み合わせは特に大型生物に甚大な被害をもたらしました。
オーストラリア大陸でおきた大型動物の絶滅はホモサピエンスが残した最初の重大な痕跡となりました。
しかしこの後も、大きな生態学的な惨事は第2波、第3波と続きます。
絶滅の第2波について
絶滅の第2波は約1万6000年前にホモサピエンスが「アメリカ大陸」に上陸したことによって引き起こされます。
ホモサピエンスは西半球の大陸に到達した最初で唯一の人類種です。
当時、シベリア北東部とアラスカの北東部は地続きとなっていたため徒歩で渡ることができました。
「歩いて渡った」と聞くといとも簡単にやってのけたように聞こえますが、海を渡るオーストラリア大陸への移動より大変なことです。
北シベリアは冬は全く日が昇らず、気温は−50度まで下がりうるため極端な寒さに順応する必要がありました。
比較的寒さに順応していたネアンデルタール人でさえ到達することは不可能でした。
しかしホモサピエンスは独創的な解決方法を生み出しました。
寒さを凌ぐための知恵
- 雪の上を歩くための履き物を作る
- 針を発明する
- 何重にも重ね、針でしっかりと縫い合わせた毛皮や皮革からなる保温効果の高い衣服を作る
さらには極北の大きな獲物を捕獲するための新しい武器と高度な狩猟技術を開発することで、北への移動を可能にしました。
さらに1万4000年ごろに地球温暖化がおき、氷が溶けたため道が開け、さらに南へと進んで行きました。
ホモサピエンスがアメリカ大陸に上陸してからおよそ2000年の間で
北アメリカでは大型哺乳類47属のうち、34属が
南アメリカでは60属のうち40属を失ってしまいました。
認知革命の時に200属生息していた、体重50kgを超える大型哺乳類は
農業革命の時には100属ほどしか残っていませんでした。
絶滅の第3波について
絶滅の第3波は200年前に産業革命が起きたことによって引き起こされており、現在継続中です。
現在動植物や海洋生物が絶滅の一途を辿っているのには、私たちが社会活動や資本主義活動を行う際に生み出す「温室効果ガス」が大きな原因となっています。
簡単にいうと、温室効果ガスが増えると環境破壊が進み、生態系を崩すために動植物の絶滅に繋がってしまいます。
わたしたちにできることは?
現在、多くの動物種や海洋生物の絶滅が危惧されていますが
人類の歴史を振り返ってみると過去にも2度の大きな絶滅を引き起こしていたことがわかりました。
現在進行中の地球温暖化や動植物の絶滅は1人の力ではどうすることもできない問題であります。
しかし歴史から学びひとりひとりが自分事として考える、意識を変えるということが非常に大切なのではないでしょうか。
私が実際行なっている取り組み
私が実際に地球環境を守るために微力ながら行なっている取り組みはこちらです。
- 段ボールやペットボトルやトレーなどの資源ごみは可能な限りリサイクルに出す
- 外出する時は水筒を持参しペットボトルの飲み物を買わない
- 肉を極力食べない
- 物を買わない
- 無駄な消費を抑える などなど
些細な取り組みですが一人一人の意識を変えることが大切なことだと思います。
みなさんもぜひ身近なことから少しずつ挑戦してみてください。
さいごに
いかがでしたか?
地球上におきた3回の大きな動植物の絶滅について知ることができたかとおもいます。
おさらいしておくと
絶滅の第1波 → 約4万5000年前にホモサピエンスがオーストラリア大陸に上陸したことによって引き起こされた
絶滅の第2波 → 約1万6000年前にホモサピエンスがアメリカ大陸に上陸したことによって引き起こされた
絶滅の第3波 → 約200年前に産業革命が起きたことによって引き起こされ、現在も継続中
となります。
人類史のことでは一通り伝えたい記事は書けました。笑
これからまた日本史の記事を書いていこうと思いますので
引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
最後まで読んでくださりありがとうございました!